精進落としをご存知でしょうか。
本記事では、初七日法要や火葬後に行われる会食である精進落としの意味や由来、挨拶の有無について解説します。
精進落としとは
精進落としは、故人を偲び、法要や火葬後に行われる会食です。
お世話になった僧侶や参列者、親族への感謝とおもてなしの意味が込められています。
もともと精進落としでは、仏教の教えに従い、肉や魚を避けた精進料理がふるまわれていました。
しかし、現在では、刺身や寿司、懐石料理などが出されることも増えています。
現代の精進落としは、葬儀や法要が無事に終わったことへの感謝や労いの気持ちを示す場としての意味合いが強まっています。
精進落としの由来
精進落としは、かつて四十九日の法要後に食べる日常の食事を指していました。
遺族は命日から四十九日まで、故人が極楽浄土へ導かれることを祈って、肉や魚を避けた精進料理を食べ、故人のために徳を積むという意味もあります。
また、かつての日本では「死」は穢れと考えられ、喪中の間、遺族は「別火(べつび)」といって、日常の火を避けて生活する習慣がありました。
さらに、忌中には別の小屋にこもり、生活そのものを分ける風習もありました。
特別な生活から通常の生活に戻る象徴として行われたのが「精進落とし」です。
特に四十九日が過ぎ、遺族が精進料理から普段の料理へと切り替える際に行われます。
精進落としの挨拶の有無
精進落としの場では、最後に挨拶をすることは一般的ではありません。
お弔いの後の席では、特に締めの挨拶は避けるべきとされています。
大切なのは故人を偲びつつ、これまでの支援や尽力への感謝の気持ちを伝えることです。
また、今後の穏やかな日々を願う気持ちを込めて、感謝と支援の気持ちを丁寧に表現することが求められます。
正式な「挨拶」とは異なり、最後のお別れの際の労いの言葉が適切です。
まとめ
今回は精進落としの意味や由来、挨拶の有無について解説しました。
葬儀はマナーなど専門的な知識が役立ちます。
ご検討中でしたら葬儀専門家へ相談することを検討してみてください。
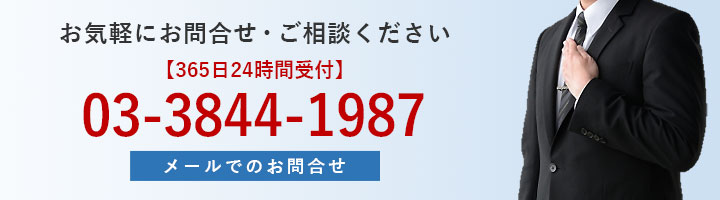
 社葬の流れ
社葬の流れ
 大型葬の流れ
大型葬の流れ
 家族葬メリットデメリット
家族葬メリットデメリット
 家族葬でありがちなトラ...
家族葬でありがちなトラ...
 家族葬はお通夜なしでも...
家族葬はお通夜なしでも...
 社葬を執り行うまでの段...
社葬を執り行うまでの段...
 家族葬の斎場
家族葬の斎場
 葬儀スタイルによる違い
葬儀スタイルによる違い